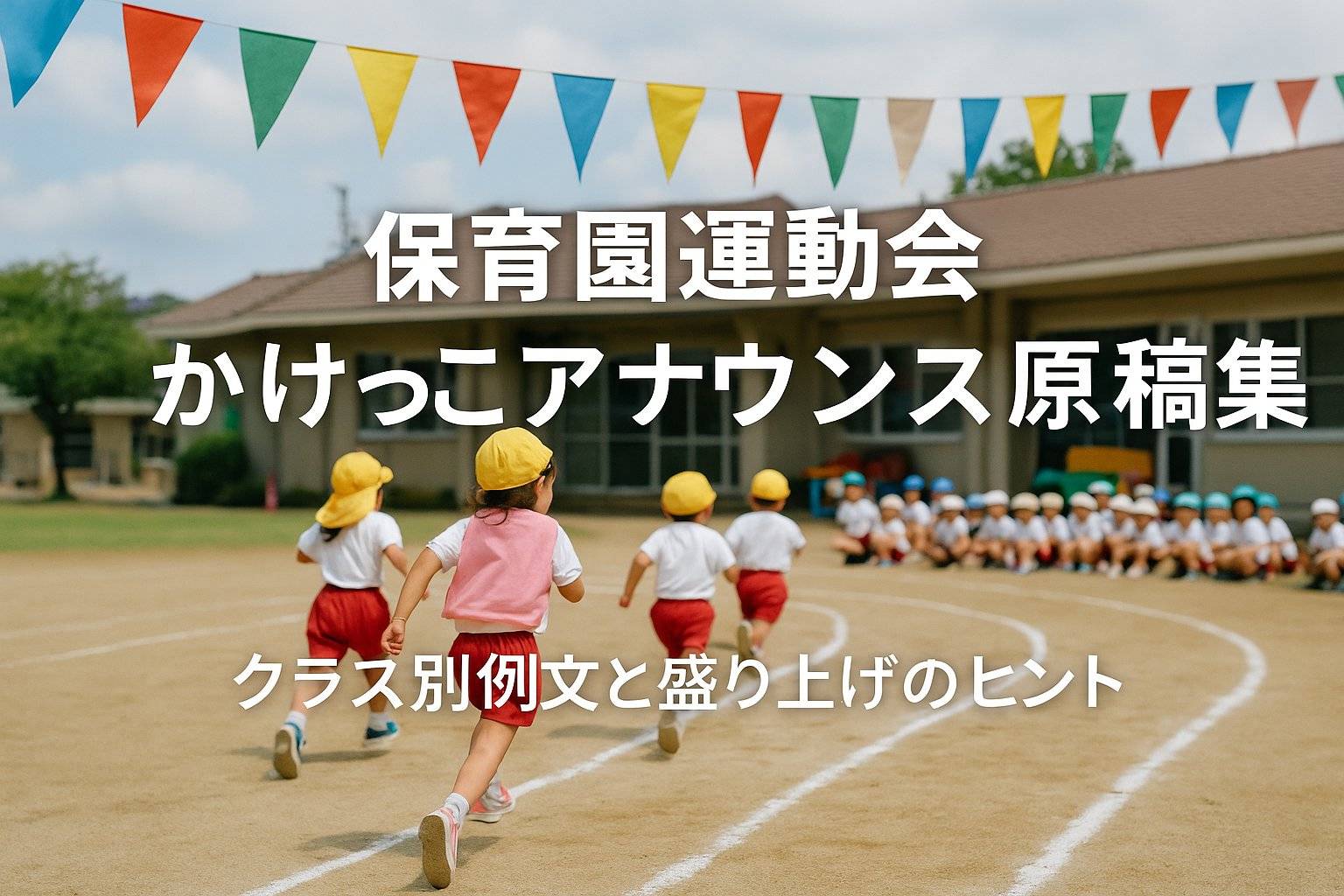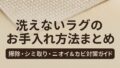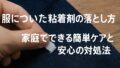運動会の「かけっこ」アナウンスを任されると、どんな言葉を使えばいいのか悩んでしまいますよね。
特に初めて担当する方は不安も多いと思います。
この記事では、保育園のクラス別アナウンス原稿例をはじめ、アドリブの入れ方や保護者が喜ぶフレーズ、準備のコツまでをやさしく解説します。
初心者の方でも安心して読める内容になっていますので、ぜひ参考にしてくださいね。
保育園の運動会アナウンス全体の流れ
運動会のアナウンスは、最初から最後まで流れを意識して進めるとスムーズです。
- 開会のあいさつ(今日一日の流れや注意点を簡単に伝える)
- かけっこなど種目の紹介(出場する子どもの名前や学年をはっきり伝える)
- 競技の合間のコメント(子どもの頑張りや観客への感謝を添える)
- 閉会のあいさつ(全体のまとめや最後の労いの言葉をかける)
開会では元気に声を出して会場の空気を和ませることが大切です。
種目紹介では、子どもたちが誇らしい気持ちになれるように笑顔を交えて伝えるとよいでしょう。
競技の合間には、会場の雰囲気を温かく保つために「皆さん、大きな拍手をお願いします」などの一言を添えると盛り上がります。
閉会のあいさつでは、保護者や先生方への感謝を忘れずに伝えることで、全体が心地よい余韻に包まれます。
特に「かけっこ」は運動会の中でも盛り上がる種目なので、子どもたちが安心して力を発揮できるよう、元気に楽しい雰囲気を伝えることを意識しましょう。
保育園のかけっこアナウンス原稿例【クラス別】
2歳児クラス編
「ただいまから、2歳児クラスのお友だちによるかけっこです。
小さな足で一生けんめい走りますので、大きな拍手で応援してください。
まだ歩くこともおぼつかない年齢ですが、一歩一歩が大きな成長の証です。
かわいらしい表情や転びそうになりながらも前へ進む姿に、ぜひ温かい声援を送ってあげてください。」
3歳児クラス編
「次は3歳児クラスのお友だちです。
元気いっぱいに走る姿をどうぞご覧ください。
最後までがんばれー!
少しずつ走るスピードも速くなり、友だちを意識しながら走る姿は頼もしく感じられます。
応援を受けると笑顔でさらに力を出す子も多いので、どうぞ盛大な拍手で盛り上げてください。」
4歳児クラス編
「4歳児クラスのお友だちがスタートします。
スピードも出てきて迫力満点です。
ゴールまで力いっぱい走り抜けましょう!
体力もついてきて競争心も芽生える時期ですので、真剣な表情で走る姿が見られると思います。
最後まで諦めずに走る子どもたちに、大きな声援をお願いします。」
5歳児クラス編
「続いては5歳児クラスです。
もうすぐ小学生になる頼もしい姿をお見せします。
最後まで全力で走る姿にご声援をお願いします。
しっかりとしたフォームで力強く走る姿は、小学校への期待を感じさせます。
ゴールテープを切る瞬間には達成感あふれる笑顔が広がりますので、ぜひその瞬間を逃さず応援してください。」
かけっこのアナウンスでアドリブを入れるコツ
- 子どもの頑張っている様子をその場でコメントする
- 例:「にこにこ笑顔で走っていますね」「一生けんめいゴールを目指しています」など、その瞬間の様子を拾うと臨場感が出ます。
- 保護者に声をかける
- 例:「カメラのご準備もお忘れなく」「温かい声援が力になります」など、会場全体に呼びかけると一体感が生まれます。
- 安全への配慮を盛り込む
- 例:「ゴール付近はお子さまの走行を妨げないようにお願いします」「小さなお子さまはコースに入らないようご注意ください」など、自然に安全確保につなげます。
- 天候や雰囲気に合わせた言葉を添える
- 例:「少し風が強いですが、みんな負けずに走っています」「おひさまも応援してくれているようですね」など、会場の空気に合わせた一言が効果的です。
- 子どもの名前や特徴を取り入れる
- 例:「〇〇くんがんばっています」「笑顔で走る〇〇さんに大きな拍手を」など、個別の声かけは特別感があり保護者にも喜ばれます。
アドリブは短くてシンプルな言葉で十分です。
無理に話そうとせず、感じたことをそのまま伝えると自然になりますよ。
緊張しても、深呼吸をして子どもたちの姿に集中すれば、自然な言葉が出てきます。
慣れてきたらユーモアを少し混ぜたり、観客の反応を拾って返したりすると、より雰囲気が和やかになります。
保護者が喜ぶ一言フレーズ集
- 「お父さん、お母さんの声援が力になります!」
- 「今がシャッターチャンスです!」
- 「みんな最後までがんばりました。大きな拍手をお願いします!」
- 「ゴールまであと少しです、最後まで応援してください!」
- 「がんばる姿をたくさん写真に残してくださいね」
- 「応援の声が子どもたちの力になりますよ」
ちょっとした一言を添えるだけで、会場全体が温かい雰囲気になります。
フレーズの種類をいくつか持っておくと、場面に合わせて使い分けができ、より自然に盛り上げることができます。
ときには保護者に「一緒に手を叩きましょう」と促すと、会場が一体となり、子どもたちにとって忘れられない思い出になります。
先生・保護者がアナウンスする場合の違い
- 先生が読むとき:落ち着いたトーンで、子どもたちを安心させる言葉を意識する。
子どもの名前をていねいに読み上げたり、安心感を与える声かけを大切にすると良いでしょう。 - 保護者が読むとき:にぎやかに、応援を引き出す雰囲気作りを意識する。
明るい笑顔や弾んだ声で話すと、自然に会場全体が盛り上がります。
立場によってトーンを変えると、アナウンスがより自然になります。
先生は子どもたちの安心を優先し、保護者は楽しい空気づくりを優先する、という意識で読み分けると効果的です。
かけっこを盛り上げる選曲ポイント&おすすめ曲5選
選曲のポイント
- テンポが明るくリズムが取りやすい曲
- 子どもたちが知っている曲
- ゴールに向かって気分が高まる曲
- 保護者世代にもなじみがある曲を混ぜると一緒に楽しめる
- 盛り上がる部分と落ち着く部分のメリハリがある曲も効果的です
音楽は会場の空気を一瞬で変える力を持っています。
リズムに合わせて手拍子が自然に起こったり、知っている曲が流れると子どもも安心して力を出せます。
短い距離でも音楽があることで印象が大きく変わるので、選曲は雰囲気づくりの大切な要素です。
おすすめ曲例
- 『アンパンマンのマーチ』
- 小さな子から大人まで知っている定番曲。明るい歌詞とテンポでスタートにぴったりです。
- 『さんぽ』(となりのトトロ)
- 楽しく歩く・走るイメージがぴったり。和やかな雰囲気にしたい時におすすめです。
- 『勇気100%』
- 子どもたちを元気づける定番曲。力いっぱい走る気持ちを後押しします。
- 『ミッキーマウスマーチ』
- 行進やスタートの合図に使いやすい。観客も一緒に盛り上がれる明るい曲です。
- 『パプリカ』
- ダンスでおなじみの曲。みんなが口ずさめるので一体感が生まれます。
- 『となりのトトロ メインテーマ』や『ドラえもんのうた』などアニメ曲
- 子どもも保護者も楽しめる親しみやすい選曲で、幅広い年齢に受け入れられます。
曲を流すタイミングも工夫するとさらに効果的です。
スタート直前には明るくテンポの良い曲を、ゴール間近では盛り上がりが最高潮になるようなフレーズを流すと、自然と応援の声が大きくなります。
失敗しないアナウンスのための準備チェックリスト
- 原稿を印刷して持っておく。ページをめくりやすくまとめておくと安心です。
- 子どもの名前の読み方を確認しておく。難しい漢字や読み間違えやすい名前は特に注意しましょう。
- マイクの音量を事前にチェック。実際に声を出して会場の隅まで届くか確認すると安心です。
- ゴールテープやコースの安全確認をしておく。テープが絡まないか、転倒しやすい場所がないかを事前に見ておきましょう。
- BGMの流す順番や音量も事前に確認しておくと安心です。音量は会場の広さや外の環境音も考慮するとよいです。
- 進行表やタイムスケジュールを手元に用意して、次の競技をスムーズに案内できるようにしておきましょう。
- 水分補給やのど飴なども事前に準備しておくと声の調子を保てます。
ちょっとした準備で当日の安心感が大きく変わります。
さらに、予備の原稿や替えのマイクなど、万が一に備えておくことでより余裕を持って臨めます。
かけっこのアナウンスを成功させる練習法
- 声を出して読む練習をする。できれば実際にマイクを持って練習すると本番に近い感覚がつかめます。
- ゆっくり、はっきり話すことを意識する。緊張すると早口になりがちなので、意識的にペースを落としましょう。
- 鏡の前で読んでみて表情を確認。笑顔で話す練習をすると声の印象も明るくなります。
- 家族や友人に聞いてもらって感想をもらう。聞き手の立場での意見はとても参考になります。
- スマホで自分の声を録音して聞き返す。改善点が客観的に見えてきます。
- 実際に会場に立ち、声を響かせてみるシミュレーションも効果的です。
短時間でも練習しておくと、本番で落ち着いて話せます。
何度か練習を重ねておくと自然に声に自信がつき、安心してマイクを握れるようになります。
よくある質問(FAQ)
Q1:アナウンスは原稿をそのまま読んでもいい?
A:もちろん大丈夫です。特に初めて担当する方は、原稿を読みながらでも十分安心して進められます。
慣れてきたら少しアドリブを入れると雰囲気が和み、子どもたちの表情や観客の反応に合わせて柔軟にコメントできるようになります。
Q2:名前を読み間違えたらどうすればいい?
A:落ち着いて訂正すれば大丈夫です。笑顔でフォローすると場も和みます。
「失礼しました、〇〇さんでしたね」とやさしく言い直すと、会場全体も温かく受け止めてくれます。
事前に名簿で確認することも大切ですが、間違えても慌てずに対応すれば問題ありません。
Q3:盛り上げすぎてしまうのはNG?
A:基本的には明るく盛り上げて大丈夫です。
ただし、安全への配慮は忘れないようにしましょう。
例えば、応援の声が大きすぎて子どもの声が聞こえなくなったり、走行の妨げになる場合は注意が必要です。
楽しい雰囲気を大切にしつつも、落ち着きや安全の確保を優先するバランスが大切です。
Q4:緊張して声が震えてしまったら?
A:誰でも最初は緊張します。
深呼吸をしてから話し始めたり、最初の一言をゆっくり言うことで落ち着きを取り戻せます。
会場の人は温かく見守ってくれるので、失敗を恐れずに安心して臨みましょう。
Q5:どれくらいの声量で話せばいい?
A:会場の一番後ろにいる人に届くように、はっきりと大きめの声で話すのが基本です。
マイクの音量も事前にチェックして、声が小さすぎたり大きすぎたりしないように調整しておきましょう。
まとめ
保育園の運動会アナウンスは、元気に楽しく、そして子どもたちを安心させることが大切です。
クラス別の原稿例をベースに、アドリブや保護者向けのフレーズを少しずつ加えることで、自然で温かい雰囲気が作れます。
また、音楽や準備、練習の工夫を取り入れると、よりスムーズで安心できる進行が可能になります。
初心者の方でも、この記事のポイントを押さえれば落ち着いてアナウンスできます。
しっかりと準備を整えて臨み、子どもたちと一緒に素敵な思い出を作ってくださいね。